【先行き不透明な経済への不安から?】若年層でも拡大!ワンルームマンション投資とは?

投資への興味・関心が高まっている近年、若年層のうちから資産運用を始める人が圧倒的に増えています。
例えば、ワンルームマンション投資の話をしていて興味をもった友人が、
ネットで検索をかけると、マンション投資はやめとけ とか ワンルーム投資はおすすめ という二極化の検索結果が出て来てきます。
実際のところはどうなのでしょうか。
当然、投資なのでリスクはつきものです。
リスク内容 と その対策 をしっかりと認識して、投資を始めていきましょう。
今回は、ワンルームマンション投資とはどういったものなのかという概要をお伝えし、詳しく解説
していきます。
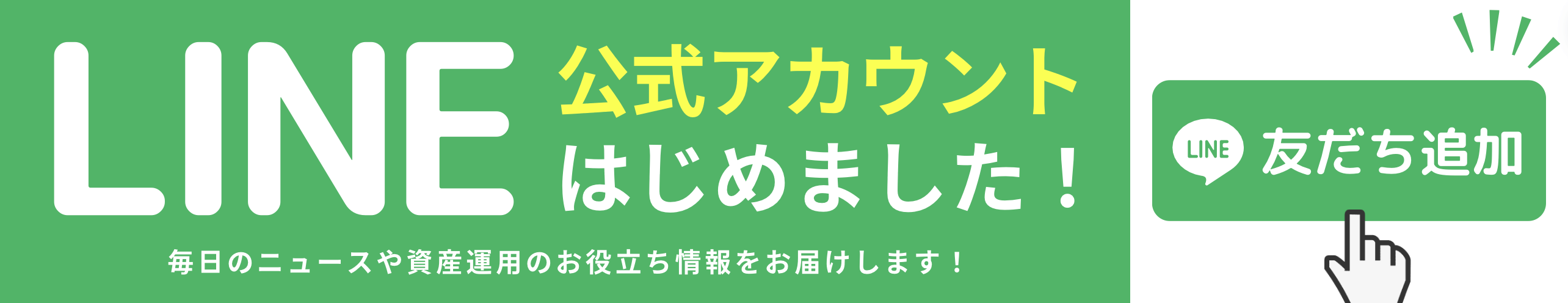
ワンルームマンション投資とは?

マンション投資の仕組み
ワンルームマンション投資とは、1K や 1R といった単身者(独身者)用の分譲マンション1戸を購入して第三者に貸し出して、その賃料を得るというシンプルなものです。
しかしながら、分譲マンションでは管理費や修繕積立金、固定資産税がコストとしてかかります。したがって、賃料収入からこうしたコストを差引いた部分が儲け(プラス)になります。
これが、ワンルームマンション投資の簡単な概要です。
マンション投資の支出
ワンルームマンション経営で支出となる項目は以下の通りです。
- 1.賃貸管理会社への管理費用
- 2.固定資産税、都市計画税
- 3.保険料
- 4.修繕費用
- 5.ローン返済
マンションの管理会社に賃貸管理業務を委託した際、管理費用がかかります。
一般的には、管理費用は月々の家賃収入のおおよそ3%~5%です。
物件を所有していることにより、固定資産税や都市計画税の支払義務が発生します。
一般的に、2月・6月・9月・12月の年4回に分けて支払います。
火災保険、地震保険、賠償責任保険などの保険加入の費用がかかります。
対象となる物件や保険への加入期間によって金額が変わってきます。
建物外壁のひび割れ、塗装の剥がれ補修 や 照明器具などの交換にも費用がかかります。
不動産投資ローンを利用している場合は、ローン返済を行わなければなりません。
借入金額と借入期間、金利によって月々の返済額が変わります。
ワンルームマンション投資のデメリット(リスク)

空室になることで家賃収入がゼロになる
ワンルームマンション投資はその名の通り、マンションの1室を購入し、その部屋を第三者へ貸し出して、家賃収入を得るというものです。
しかし、購入したその部屋になかなか次に住んでくれる人(入居者)が見つからなかった場合、家賃収入はゼロになります。
家賃収入が無くても、不動産会社への管理費用や銀行へのローン返済はしなくてはなりませんので、家賃収入でまかなうことを想定していた支出を全て自身で支払わなければならなくなります。
一方で、1棟アパート・マンションであれば、物件価格はワンルームマンション投資と比べて格段に高くなるものの、部屋が複数あるため、家賃収入を1部屋に依存せずに済み、空室リスクの分散が期待できます。
経年劣化で修繕が必要になる
「経年劣化」とは、年月が経つにつれて品質が下がることを言います。たとえば、陽の光があたると建物の壁や床が色あせてきたり、風や湿気によってゴムやネジが傷んだりすることです。こうした時間の経過とともに自然と劣化していくのが、賃貸物件における「経年劣化」というものです。
これら経年劣化によって発生する修繕費用は、原則として大家さん(貸主)が負担するものとしています。経年劣化の費用はすでに賃料に含まれている、という考えが基本にあるためです。

ローンの金利が上がると、支払総額が上がってしまう
ローンは、知識のある・なしで、得をする人もいれば、損をする人もでる重要なものです。
そこで、ローン選びでまず心得ておきたいのは、「金利」です。
金利差0.1%で、返済額にどれくらいの違いが出るかを見ていきましょう。
例えば、借入額が4,000万円とした際の試算をしてみましょう。
- ・金利0.4%:4,287万円(月10.2万円返済)
- ・金利0.5%:4,361万円(月10.4万円返済) +74万円
- ・金利0.6%:4,436万円(月10.6万円返済) +148万円
- ・金利0.7%:4,511万円(月10.8万円返済) +224万円
〈例1〉借入額4,000万円、借入期間35年(元利均等払い)
このように、金利差0.1%で74万円の違いが出てきます。
金利が0.1%高いだけで、これだけの支出が発生してきます。金利が0.7%(0.3%のアップ)だと、224万円も返済額が増えます。
下記の表は、借入金額別に返済額にどれだけの違いが出るかをまとめたものです。借入期間は35年想定としています。
返済額の変化表
| 借入額 | 返済額 | |||
| 金利 0.4% | 金利 0.5% | 金利 0.6% | 金利 0.7% | |
| 2,000万円 | 2,144万円 | 2,181万円 37万円増加 | 2,218万円 74万円増加 | 2,256万円 112万円増加 |
| 3,000万円 | 3,215万円 | 3,271万円 55万円増加 | 3,327万円 111万円増加 | 3,383万円 168万円増加 |
| 4,000万円 | 4,287万円 | 4,361万円 74万円増加 | 4,436万円 148万円増加 | 4,511万円 224万円増加 |
| 5,000万円 | 5,359万円 | 5,451万円 92万円増加 | 5,545万円 186万円増加 | 5,639万円 280万円増加 |
| 6,000万円 | 6,431万円 | 6,542万円 111万円増加 | 6,654万円 223万円増加 | 6,767万円 336万円増加 |
| 7,000万円 | 7,503万円 | 7,632万円 129万円増加 | 7,762万円 260万円増加 | 7,895万円 392万円増加 |
| 8,000万円 | 8,574万円 | 8,722万円 148万円増加 | 8,871万円 297万円増加 | 9,022万円 448万円増加 |
借入額が8,000万円の場合、金利が0.4%と0.5%の差は、返済額で148万円です。金利が0.7%(+0.3%)だと、448万円も返済額が増えます。
この表で、金利0.1%の違いがよく分かるのではないでしょうか。住宅ローンを選ぶうえで、圧倒的に注意しなければならないのは金利なのです。
また、すでにローンを返済中の人にとっては、金利上昇によって、返済額がこれだけ増えるということになります。
ちなみに、手数料は金融機関によってかなりバラつきがあります。しかし、高い手数料の場合でも、借入金額が2,000万円なら、手数料は44万円です。これは上の表を見ると、金利差0.1%とほぼ同じ金額です。
同じ金利タイプの商品でも、金利が高い金融機関と低い金融機関では1%以上金利差があることはよくあります。「手数料が無料」「手数料が一律で安い」というキャッチフレーズに惑わされるのではなく、まずは金利が低いローンを探すことが重要となってきます。
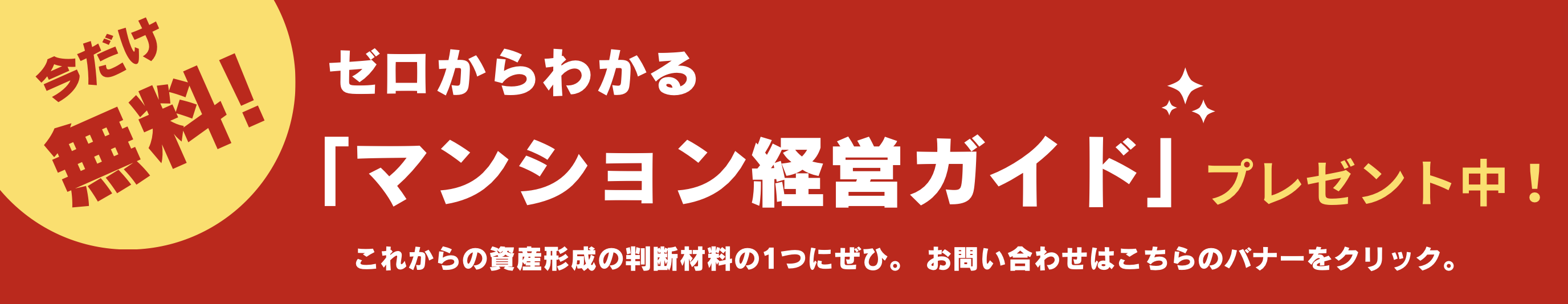
入居者がついても、家賃が滞納されるリスクがある
意外と思われるかもしれませんが、家賃の滞納は、賃貸経営をしていると高い確率で経験する可能性があるリスクです。
当然、家賃を通常通りに支払う入居者がほとんどですが、一般的には、約2%~3%の入居者が家賃を遅滞する可能性があると言われています。
これは、単なる振り込み忘れ等のすぐに解決するような滞納ではなく、ある程度の期間に渡って滞納してしまうケースです。
少ないと感じるかもしれませんが、規模を拡大する程、滞納リスクは上がるため、将来的に100世帯以上を所有するような投資家を目指したい人は、必ず意識するべきリスクです。
現在は少し緩和されてきていますが、コロナウイルスの影響もあり、収入が激減している世帯も少なからずあるので、家賃滞納リスクは、確実にあります。
コロナの影響は、かなりイレギュラーなケースにはなりますが、今後はそのようなイレギュラーな事態にも備えておく必要があります。
「家賃滞納があってもすぐに取り立てれば問題ない」、「滞納した時点で退去してもらえば大丈夫」等、家賃滞納のリスクをあまく見ている投資家は意外と多いです。
家賃滞納リスクは、そこまで単純なものではなく、実際に起こると解決するまでに時間も費用も労力もかかる大変なものです。
①家賃滞納があってもすぐに退去となるわけではない
「家賃を滞納した時点で退去してもらえば良い」と考える人が多いです。しかし、家賃を滞納した入居者がいたとしてすぐに退去を要請が出来るかというと、実はそうでもありません。
日本では、借地借家法という法律があり、投資家であるオーナー側と比較して入居者にあたる賃借人は強く保護されています。
具体的な実務に落とし込むと、立ち退きを要請するには少なくとも3カ月以上の滞納歴が必要となります。
また、3カ月の滞納があった時点で退去要請が出来るかというと、そうではありません。
退去を要請するには、裁判所に訴訟を提起する必要があります。強制退去にまで発展した場合、はじめての滞納があってから退去まで1年近くかかるというケースも少なくありません。
滞納というと「入居者の責任でありオーナー側が損をするなんて。。」と思っている人も多いですが、そうではないということを頭に置いておきましょう。
②退去要請は時間も費用もかかる
家賃滞納をしている入居者を退去させるのは、容易なことではありません。
多くの場合、オーナー側が時間と費用と労力をかけて解決させていくケースがほとんどです。
退去要請は、時間だけでなく多くの費用も発生します。
裁判所に支払う訴訟費用や強制執行費用だけでも、それぞれ約30万円~40万円が必要になり、それだけでも大きな損害と言えます。
さらに、振り込まれない家賃分が課税対象になった場合、その分の所得税や住民税も負担する必要があります。
例えば、賃料によりますが、総額で100万円を超える損害になることも珍しくありません。
そのため、不動産投資の中で家賃滞納は、単に家賃が入ってこない空室よりも怖いリスクと言われています。
しかしながら、事前の防止策によってある程度回避することは可能です。
例えば、立地が良い物件で一定数の需要が見込まれるところなどを選ぶことも、防止策の一つになるでしょう。
地震が起きて、建物に被害が出る可能性がある
地震や台風といった自然災害によるリスクは、完全に回避することは不可能です。しかし、地震のリスクは立地や建物の性質に大きく関係するため、購入時に以下のようなポイントに注意して物件を選ぶことで、リスクを最小化することが可能となります。
物件の耐震性を最低限保証する耐震基準には、
①新耐震基準
②旧耐震基準
の2つがあります。
地震に強い物件を選ぶ際、①新耐震基準 が適用されて建設された物件かどうかを確認することが必要です。
新耐震基準とは、1978年に起きた宮城県沖地震を教訓として、震度6強の大地震でも倒壊しないことを前提としています。
ちなみに、東日本大震災にて倒壊したマンションは0棟、熊本地震にて倒壊したマンション1棟です。
- ・棟数:85,798棟、管理戸数:4,295,636戸
- ・大破は0棟、中破は61棟(0.071%)、小破は1,070棟(1.247%)
(参照:東日本大震災 被災状況調査報告) - ・棟数:7,610棟
- ・大破は1棟(0.02%)、中破は5棟(0.08%)、小破は151棟(2.53%)
(参照:九州地方における会員受託マンションの被災状況の概要について)
【東日本大震災】
【熊本地震】
過去、史上最大の地震でも倒壊は0棟でした。残念ながら熊本地震では1棟倒壊しておりますが、このマンションは昭和47年~56年に建てられたもので昭和56年に施行された新耐震基準以前のものとなります。
従来の旧耐震基準では、震度6強の大地震に対して特に規定されておらず地震リスクがかなり高いと言えます。1982年以降に建てられた物件であっても旧耐震基準に則っている場合があるため、建築年のチェックのみでなく耐震基準を確認しましょう。
また、旧耐震基準に則っていながらも丈夫に作られていたり、新耐震基準に則っていながらも施工ミスなどで耐震性が低かったりするケースもあります。
物件を選ぶ際、その場所が地震に強い土地かどうかは、重要な判断材料となるでしょう。しかしいくら地震に強い場所といっても、その場所に一極集中で、複数の物件を購入することはあまりおすすめできません。
投資効率を考えるのであれば、確かに、一極集中の投資の方が優れています。しかし、地震に強いエリアでも被害に合う確率はゼロではなく、地震以外の台風といった災害も考慮に入れれば、一極集中の不動産投資はかなりリスクが高いです。リスクヘッジの観点からも、投資エリアを選定する際、地域を分散させることがおすすめです。
不動産会社が倒産する
不動産投資によるマンション経営の魅力の一つに、面倒な管理業務を管理会社にお願いできるところがあります。
しかし、「管理会社が倒産したらどうなるの?」と不安を感じる人もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、不動産管理会社が倒産するリスクはかなり低いです。
なので、管理会社の倒産リスクを恐れて、自主管理を行い、空室発生時の入居者募集や入居者からのクレーム対応などを365日体制で行うより、客付けの強い管理会社に管理業務を任せた方が、自分は、本業に集中して効率的なマンション経営を行うことができるのでおすすめです。
管理会社は安定した管理手数料を収益源とするため、倒産リスクはかなり低いと言われていま
す。
しかし、本業が別の事業、たとえば飲食業や旅行業などである場合、話は異なります。
飲食業や旅行業などは収入の変動が激しい業種です。
昨今の新型コロナウィルスの影響を受けやすいこともあり、急激な業績悪化によって倒産に至る可能性も考えられるでしょう。
そのため、管理会社の主軸となる事業が不動産業以外の場合は要注意です。
不動産価値の下落リスク
投資マンションは、自分が住むためではなく入居者である第三者に賃貸するために購入するものですので、必ずしも新築である必要はありません。
新築マンションは、中古と比べて3割以上も割高な金額となるため、購入した瞬間から割高なローンを組んでしまうことになります。新築物件の価格には、ディベロッパーや販売会社の宣伝広告費(テレビCMやパンフレット、物件のWEBページ費用)、建築するまでの人件費、建築費、建築会社利益が上乗せされています。また、新築価格はディベロッパーが独自に価格設定をしています。
そのため、自身の収入を考慮して、中古か新築かを選んでいきましょう。まずは気軽に不動産会社に聞いてみるのも良いかもしれません。
購入して所有者の登記が入った瞬間から「中古」となるため、新築で買った物件を数年後に売却しようとしても、その価格で売れないのでローンが残ってしまいます。これは不動産投資でよくある失敗事例の1つです。
下落リスクを防ぐコツとして、一般的に以下のようなものが挙げられます。
①建物周辺の人口状況や開発計画についてチェックする
②賃貸需要の底堅い立地を選ぶ
実際に物件を選ぶ前に、選ぼうとしている地域の人口状況について、調べておきましょう。
現在人口が増加傾向にあるのであれば、今後も人口増加が見込めます。
また、大きな開発計画があるような地域であれば、利便性の高まりに伴い、人口が増えていくことも見込めます。
ワンルームマンション投資での失敗

都合のいい予測を立ててしまった
以下は失敗に至ってしまった一例の紹介となります。
「空室が多いものの、〇〇の特需で今が買い時である」と勧められたAさん。確かに今は空室が多いですが、「〇〇による特需は間違いなく来て、その時に高く売却すれば問題ない」と購入を決意しました。しかし、賃貸に出しても借り手がつかず、思うような特需の恩恵は受けられませんでした。
この場合は、理想が大きすぎて現実と乖離が発生してしまった、甘い予測が原因でしょう。
自分にとって都合の良い予測ばかりして、冷静に判断できなくならないように注意することが重要で
す。
利回りしか見ず、予想外に出費がかさんだ
不動産投資は安定した家賃収入が魅力ではあるものの、空室が生じると肝心の家賃収入が得られ
なくなってしまいます。
例えば、アパート1棟を購入し、それを運用して80%ぐらいの稼働率を想定していたとします。
ところが、60%、50%とどんどん稼働率が低下してしまう場合があるとします。そうなってくると、当初計画していた返済シミュレーションに支障が生じ始めてしまいます。
また、ワンルームマンションを購入して運用していたところ、なかなか入居者が現れないというケースもあります。
アパート1棟とは違い初期投資は小さいものの、家賃収入が0になってしまうので、このケースも返済計画に大きな影響を与えてしまう失敗例となってしまいます。
節税目的で失敗してしまった
「節税」という言葉に飛びついてしまって、仕組みを理解せず始めてしまうことが失敗につながります。
「不動産投資で節税する」のが有効な手段となる方は、年収の高い方、年収1,500万円以上の方など、高い税率で所得税を納めている方です。
また、その方たちが節税を目的にするならば、不動産の選び方にも工夫が必要となります。
不動産会社や税理士などに相談して目的に沿った物件を選ぶことでリスクを回避することができます。
まずは、不動産会社に相談してみましょう。
初めてのワンルームマンション投資で成功するコツ

リフォームとリノベーション
中古でも構わないと考える人が多くなったとはいえ、単に古いままの物件が好まれているわけではありません。
中古物件であっても住みたくなるような価値を生み出すことが重要で、それを実現するのがリフォームやリノベーションです。
不動産の世界には、古い建物ほど立地に恵まれたものが多いという「定説」があります。
立地条件のよい土地は投資価値が高いのでマンションなどの建物が建ちやすいですが、すでに建物がある場所に新築することはできません。
後から建つ建物は残された土地しか選択肢がないため、条件に恵まれた土地を選びやすかった時期に建てられたマンションなどの建物には好立地のものが多く見られます。
しかし、築年数が古い建物は現状のままですと、集客力に欠けてしまいます。
そのため、リフォームやリノベーションによって付加価値を高めれば、好立地で良いマンション物件を生み出すことができます。
最大のメリットは、効果に対して安価であるという点です。
最新の設備が整った部屋を用意したいと思った際、新築のマンションや住宅を購入するにはかなりの費用が求められます。
一方、古い建物を安価に購入し、内装や外装だけリノベーションすれば同等の印象を与える物件を安く準備することができます。
初期投資額・コストの安さが、不動産投資の初心者にも人気な理由の1つなのです。
繰り上げ返済
繰上返済とは、毎月の決められた返済額とは別に、ローン残額の一部を返済予定より早く返済する方法のことをいいます。
予定を早めて返済を行うわけですから、その早期返済分はローン残額の元金にそのまま充当されます。
そのため、元金が減った部分の利息はそれ以降発生しなくなり、総支払額を減少させることができるようになります。
繰上返済には「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2つの種類があり、どちらを選択するかによって総支払額の削減効果は異なります。
期間短縮型と返済額軽減型の違いは、繰上返済する際に元金のどの部分に返済したお金が充当されるか、充当の仕方が異なります。
- 毎月の返済額を変えずに、繰上返済した金額分だけ期間が短くなります。
繰上返済した期間分の元金に対して支払うはずだった利息を少なくする方法です。 - 返済期間は変わらず、繰上返済した金額分が、返済期間全体の元金におしなべて充当されます。
そのため、支払うはずだった毎月の利息金額が少なくなる方法です。
①期間短縮型
②返済額軽減型
結論として、自らのリスク許容度と資産効率性を考えて、自身のお金をどこに振り分け資産を築くのかは、いかにバランスをとるかにかかっています。
特に年齢が若いうちは、資産効率性を考えて極端な余裕資金(現預金)を持つ必要はなく、その余裕資金は投資を中心に検討しつつ(繰り返しますが自身のリスク許容度と相談)、さらに余裕資金があれば繰上返済に充てるのが良いでしょう。
まとめ
ワンルームマンション投資とは、1人暮らし・単身者向けのワンルームマンションを1部屋単位で購入・運用し、毎月家賃収入を得るという投資方法です。少ない自己資金と低いリスクで始められる不動産投資として、幅広い年代・属性の方に人気があります。
しかし、ワンルームマンション投資には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットもあります。ワンルームマンション投資を成功させるためにも、事前のリスク把握・適切な対策が必要となることを覚えておくことが大切です。
また、ワンルームマンション投資を行う際には、失敗事例や成功事例を学んでおくと不動産投資が成功しやすくなります。成功事例はもちろん、失敗事例も参考にして、不動産投資を始めてみましょう。





