【2025年 最新版】初心者必見!不動産投資の始め方−失敗しないための基礎知識−

不動産投資に興味はあるけど、何から始めれば良いか分からないという方が多いと思います。
この記事では、不動産投資の基本から具体的なステップまで、初心者が安心してスタートできるように詳しく解説していきます。不動産投資で狙うべきメリットと避けたいリスクを理解し、自身に合った投資を始めましょう。
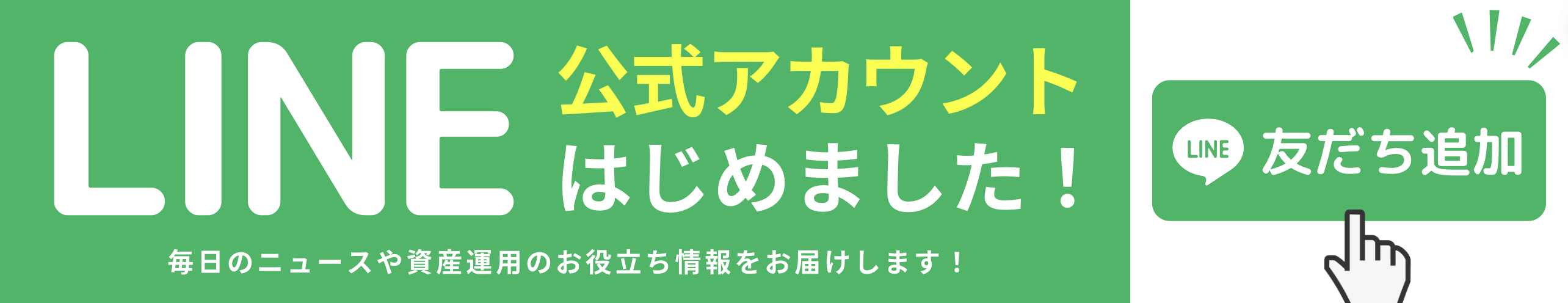
そもそも不動産投資とは?
不動産投資とは、アパートやワンルームマンション等の不動産を購入し、そこから収益を得る投資方法のことを言います。 個人が不動産投資を始める際には、多くの場合において、ローン(銀行からの融資)を利用して投資用の不動産を購入します。 その後、不動産の管理は管理会社に委託して、入居者から家賃を得ることになります。 賃料収入を確保しながら、ローンを返済していくことになるため、事前に、しっかりとした知識や計画が必要です。

不動産投資を始める前にすること
基本的な知識を身につけよう
不動産投資と聞くと、一見難しそうに感じられますが、意外とハードルは高くありません。 不動産会社や管理会社からのサポートを受けられるので、 賃貸不動産経営管理士や宅地建物取引士といったレベルの知識までは必要ありません。 もし、不動産投資について勉強してみたいというのであれば、 はじめは、ネットで調べて情報を得るのが手軽かもしれません。 その次に、まとまった知識を得る手段としては書籍を読んでみるのも良いでしょう。 書籍を読むことで、自分なりの考え方やイメージがしやすくなります。 ある程度の知識がついたら、セミナーへの参加も有効です。 専門家や投資経験者が講師となって教えてくれるので、より実践的な勉強ができるでしょう。
まずは目標を設定する
まずは、投資する不動産を探す前に自身で目標を設定しましょう。 例えば、どれくらいの収益を目指すかというイメージが事前に必要です。目標を設定すると、それだけの収益が得られる不動産がどれくらいの価格で販売されているのかわかります。購入には自己資金を準備し、そのうえでローンを組むことになるでしょう。購入可能な金額と目標収益から、より具体的な不動産のイメージができてきます。
【不動産投資の目的例】
- ・定年を迎えた時に備えて、月20万円程度の不労所得を確保しておきたい。
- ・旅行や趣味などに使うお金として、月10万円程度の副収入が欲しい。
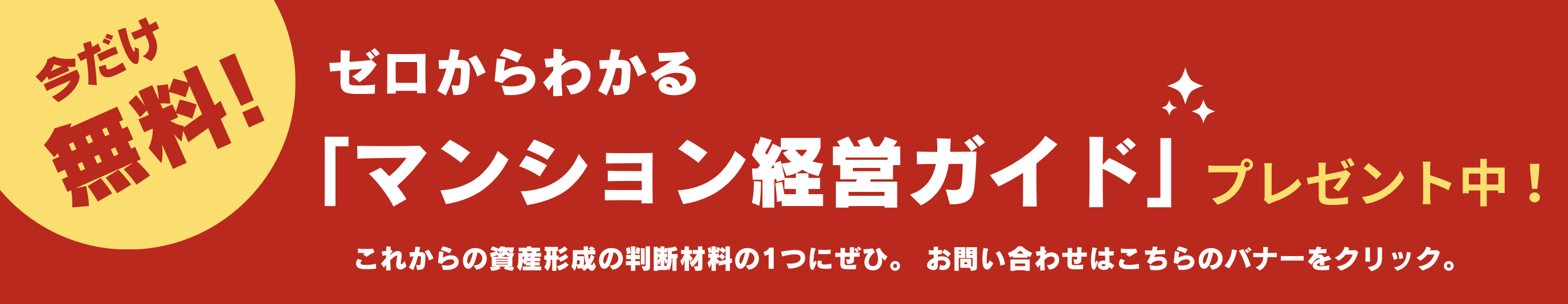
不動産投資の基礎知識

利回りとは?
投資用の不動産を選ぶにあたっては、利回りを比較してみましょう。 そもそも「利回り」とは、物件の購入価格に対して、1年間の家賃収入がどれくらいの割合になるかというものです。単純に年間の家賃収入と物件価格から算出したものは「表面利回り」と言います。また、諸費用を考慮したものは「実質利回り」と言います。 諸費用に含まれるのは、購入した際にかかる費用のほか、固定資産税、修繕費、年間運営費などが含まれます。不動産投資において「利回り」には4種類あります。物件資料を確認する際は、どの利回りのことなのかを理解しましょう。
【利回りの種類】
- ①表面利回り:投資額に対して、得られる年間家賃収入の割合
- ②実質利回り:諸経費を差し引いて、手元に残る収益の割合
- ③想定利回り:満室経営を想定した際の利回り
- ④現行利回り:現行の入居状況をベースにした際の利回り
【それぞれの計算方式】
- ①表面利回り:(年間家賃収入÷物件の購入価格)×100
- ②実質利回り:(年間家賃収入ー年間諸経費)÷(物件の購入価格+購入時の諸経費)÷100
- ③想定利回り:(満室を想定した家賃収入÷物件の購入価格)×100
- ④現行利回り:(実際の家賃収入÷物件の購入価格)×100

インカムゲインとは?
不動産投資において得られる利益は、インカムゲインとキャピタルゲインとに分類できます。 インカムゲインとは、自身の資産を保有・運用することで得られる利益(運用益)のことを言います。 不動産投資においては、家賃収入がこの「インカムゲイン」にあたります。例えば、他の投資でいうと、定期預金の利息・株式の配当金・投資信託の収益分配金などが該当してきます。
キャピタルゲインとは?
キャピタルゲインとは、自身の資産を購入した時よりも高く売却できた際に得られる売買差益(売却益)のことを言います。不動産投資では、物件の売却益がこの「キャピタルゲイン」にあたります。また、株式や債券といった金融資産や、貴金属・美術品などを売却した際に得られる利益もキャピタルゲインに該当します。
不動産投資で発生する税金
投資では、どうしても収益の部分に目が行きがちですが、納めなくてはならない税金についても、しっかり認識しておきましょう。不動産投資においては、以下の税金がかかります。
【購入時から売却まで、それぞれにかかる税金】
- ・不動産購入時:不動産取得税、印紙税、登録免許税、消費税
- ・物件運用期間:固定資産税、都市計画税、所得税、住民税、個人事業税
- ・物件売却時:譲渡所得税、住民税、復興特別所得税、印紙税、登録免許
不動産投資の種類

一棟投資
不動産投資における「一棟投資」とは、マンションやアパートなど複数の部屋がある建物全体を保有して、賃貸経営をするタイプの投資で す。 大きな土地に建物を建てることもあれば、中古を購入することもあります。複数の部屋があるため、全室が空室となり収入がゼロになるというリスクは少なくなりますが、「区分マンション投資」と比較すると難しいので、まずは、「区分マンション投資」から入るのがいいかもしれません。
区分マンション投資
不動産投資における「区分マンション投資」とは、マンション全体ではなく、戸単位で購入し、 それを賃借人に貸すことで賃料収入を得るタイプの投資です。マンションは、立地やグレードにより価格もさまざまなので、選択の幅がかなり広がります。「一棟投資」と比較すると、割と入りやすい投資ではありますが、保有が1室だけの場合、空室になっている期間は収入がゼロになるリスクもありますので、できる限り複数室持った方がリスク分散にもなるので、いいかもしれません。
戸建て投資
不動産投資における「戸建て投資」とは、アパートやマンションのような集合住宅ではなく、 一戸建ての住宅を所有して、賃貸に出し、家賃を得るタイプの投資です。土地は持っているものの、アパートなどの大きな建物が建てにくい場合などは、戸建て住宅を建てて貸します。土地と建物を所有するため、マンションの区分投資と違い、将来的に土地の値上がり益も期待できるでしょう。
不動産投資の始め方

まずは、不動産会社に相談しよう
自分なりに資産運用の勉強をして、投資の目標などが設定できたら、まずは、不動産会社に相談します。条件にあった物件を紹介してくれるでしょう。
ローン審査を受ける
購入する物件が決まったら、ローンの申請を行います。不動産投資では家賃収入を得ながら、ローンを返済していくというのが一般的な方法です。個人の信用状況とともに、その物件自体の収益性も審査に影響すると言われています。都市銀行や地方銀行などいくつか選択肢がありますが、不動産会社が紹介してくれることもありますので、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。
不動産投資に必要な書類を揃える
不動産投資のローン審査は、住宅ローンと比べて審査が厳しい点が特徴です。その理由としては、住宅ローンは、自身が住む家を購入するための融資に対し、不動産投資ローンは、アパートやマンション経営のために銀行から借りる融資となります。そのため、物件についての情報や借入後の返済に充てられる確実な資金などの返済原資も審査の 対象となるのです。物件の情報では、築年数や立地条件などが審査の対象となり、 新しい物件ほど審査に有利になることがあります。この他にも、職業や年収、年齢や勤務先、信用情報なども審査の対象となります。特にサラリーマンや公務員の方など、勤務先や勤続年数などは、融資に有利になるか・不利になるか左右される点です。勤務先は会社員の方が有利となり、大企業に勤めているか・中小企業に勤めているかなどでも変 わってきます。また、自営業や個人事業主の場合は、収入が安定しないという点で不利になってしまう場合もあります。まずは、不動産会社に相談してみて、必要な書類を聞いてみましょう。
物件を購入する
物件購入には、売り主と売買契約を締結するなど、さまざまな手続きがあります。実印や印鑑証 明、本人確認書類などの準備も必要となってきますので、頭に入れておきましょう。
管理会社との委託契約
物件を購入したら、入居者の募集をして、家賃を徴収しなければなりません。また、日常的な清掃や定期的なメンテナンスも必要になります。管理会社と委託契約を結び、すべて任せることも可能なので、物件購入の際に相談してみましょう。
運用開始
ここまでできたら実際の運用がスタートします。入居者がどれだけ集まるか、賃料収入は計画どおりか、改善の余地はあるかなどチェックしながら進めていきましょう。
不動産投資のメリットとリスクとは?

不動産投資のメリット
不動産投資において、以下のメリットがあります。
メリット1:毎月の安定した収入源
ローンの返済額よりも賃料が多ければ、毎月収入が得られるということになります。長く住んでくれる入居者であれば、安定した収益を得られる状況が続くでしょう。業務を管理会社に委託して、本業とは別に収入を得ていくことができます。
メリット2:年金対策
老後の生活資金について考えるとき、どうしても年金だけでは不足するという状況があります。不足分は貯蓄や投資などで準備することが考えられますが、手段の1つとして、不動産投資を選ぶことも可能でしょう。毎月の賃料収入で年金の不足分を補います。
メリット3:生命保険、死亡保険として活用
不動産を購入する際は、ほとんどの場合において、銀行のローン(融資)を利用します。その際、加入を求められるのが「団体信用生命保険(いわゆる、団信)」です。ローンの契約者に万が一のことがあった場合、ローンの残債がゼロになるという保険です。返済が免除され、不動産が遺族の手元に残ることになります。残された家族の生活資金に活用することができるでしょう。
メリット4:相続税対策
相続の対象となる資産は、現金で持っているより、不動産にしておいた方が税金面で有利になるケースがあります。相続税評価額は、現金の場合は額面がそのままですが、不動産において、土地は路線価方式(※)、建物は固定資産税評価額によって評価されます。例えば、固定資産税評価額だと、地価公示価格の約7割~8割の評価となるため、相続税が抑えられるのです。
※路線価が定められていない地域の場合は、倍率方式にて計算します。
参照元:国税庁No.4602 土地家屋の評価
メリット5:レバレッジ効果
不動産投資の場合、自己資金だけでなく、ローンで借りた分の金額を含めた価格の物件を購入できます。自己資金の何倍もの投資をしたことになり、少額の投資資金で大きなリターンが期待できるレバレッジ効果が利用できます。自己資金だけを運用するよりも、大きな金額を動かせるということです。
不動産投資のリスク
不動産投資において、以下のリスクがあります。
リスク1:固定費・運用費
不動産投資では、「物件の購入にかかる費用」と「毎月の賃料収入」にどうしても目が行くかもしれません。しかし、税金や修繕費といった費用が発生することにも留意しておかなければなりません。大きな破損があれば、まとまったお金も必要になってくるので、頭に入れておきましょう。
リスク2:空室
そもそも、入居者がいなければ家賃収入は得られません。何もしなくても、常に満室というのであれば特に問題はないのですが、時代にあわせた設備のアップデートなど、入居者の満足度を上げることも必要です。
リスク3:家賃滞納
たとえ入居者がいたとしても、家賃を滞納されてしまう可能性もあります。家賃収入がなくても、ローンや管理費などは支払っていかなくてはなりません。きちんと家賃を支払ってくれるかどうか、事前審査が重要となるでしょう。
リスク4:金利変動
変動金利タイプのローンを利用している場合、将来的に金利が上がると、ローンの支払額が増える可能性があります。固定金利を選択して、リスクを回避しておくことも可能です。
不動産投資の初心者が気を付けるべきポイントはここ!

購入時以外にも支出が発生する
改めての記載にはなりますが、 投資を始める際には、資金の計画を立てることがとても大切です。とくに、物件購入後にかかる費用はしっかりと把握しておきましょう。 税金や保険、修繕、運営にかかる費用など、自身が購入した物件にどれくらいの支出が発生するか、不動産会社に確認しましょう。
不動産管理会社は慎重に選ぶ
物件購入後は、「不動産管理会社に建物や入居者の管理を委託するか」、「自身で管理を行うか」のどちらかを選択することになります。業務内容にはどのようなものがあり、費用(支出)はどれくらいになるのか確認しましょう。また、入居者を集める力(集客力)があるかも重要になってきます。
ご家族の同意を先に取る
不動産投資では大きなお金の借り入れが発生することもあり、最終的に家族の同意が得られない可能性も考えられます。またアパートの運営などでは、家族の協力が必要になるかもしれません。勉強を始める際など、なるべく早い段階から家族との協力体制を作っておきましょう。
物件は印象ではなく、データで判断する
自分がこれから居住する物件を選ぶというのであれば、 見た目の印象なども重要な要素になるかもしれません。しかし投資の場合、購入金額に対してどれだけの収益を得られるのかというデータを重視しなければなりません。趣味やセンスだけに頼ってしまうと、思ったような収益を実現するのは難しいかもしれません。
不動産投資の始め方!失敗しないための基礎知識まとめ

- ①不動産投資をスタートするには知識や目標設定が大切。
- ②「利回り」「インカムゲイン」「税金」は基礎知識として理解しておく。
- ③不動産会社に相談しながら投資を進めよう。
- ④不動産投資を検討しているなら、まずは、不動産投資会社に相談することから第一歩が始まります。
わからないことや不安があれば、遠慮なく不動産会社に確認してみましょう。





